【小説風】仕事をしていた時のはなし
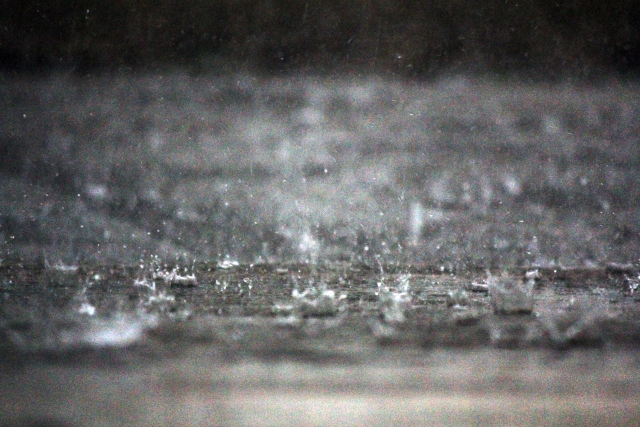
顔面は蒼白だった。電話がひっきりなしに鳴り響く都会の真ん中の高層ビルのオフィス。
いつもはその電話を、喧噪のなかに混じって私も取って、慣れた丁寧な言葉遣いで対応する。もう2年働き、毎日朝から晩まで80件ほどの電話を取り次いでいれば誰でも慣れてくる。
けれども今日は違った。そんな余裕は、砂漠の水ほどもなかった。
先月、ミスをした。傍から見ればささいなことで、こんなことに時間を費やすのはばかげた話だと誰でも思うかもしれないようなことだった。けれども、この会社、この部署にとっては、それがまるで会社の命運を決めるかのような重大案件で、私にとっては世界の終わりだった。
上司からは、次はないと言われていた。しっかり確認し、何度も確かめた。後輩のチェック、同期のチェック、そしてわたしの最終チェック。3重という、呆れるほど時間をかけて入念なチェックを行った。もう2度と同じことは繰り返すまいと心に誓いながら。
それにもかかわらず。なぜだかまたミスが起こった。なぜなのか。どうしてこうも立て続けに同じようなことをするのか。どうしてこうも私はダメなのか。先輩たちももはや私のミスに対して、何のフォローも出来ないようだった。
どうするの、と誰もが私を見ている。どうするもこうするも平謝りして、次は4重チェックをしますみたいなどうしようもない改善策を述べるしか道はなかった。
上司が目を尖らせて戻ってくる。人の目はこんなにも鋭利な刃物のようになれるのだと、私は社会人になってから知った。
とうぜん、そばを通り過ぎて自分の席に荒々しく座った上司に話しかけに行けるような隙はない。もうこのまま何も言わずに逃げ出せたらどんなにいいか。むしろもうその目で射殺してくれたらどんなに楽だったか。
けれども行かなければもっと大変なことになるのは明白だった。
先輩、同期、後輩たちの刺すような視線を背中に感じながら、私は震える手を押さえて、上司の前に立った。
申し訳ありません。最後にチェックしたのは私です。私の責任です。申し訳ございませんでした。
そう言いながら、何度も頭を下げる。意味のない謝罪だと思った。何に対して謝っているんだろう。だったらミスなんかしないでちゃんとした仕事をすればよかったのに。
こんな簡単なこと小学生でも出来ます。それなのにまた同じようなミスをして。ばかにしてるの?
上司の声には、呆れるどころではない、諦めさえ感じる。私の下げる頭も、震える言葉も、おびえるだけの目も、何もかもが、上司の気に障るようだった。そうだろう、よくわかる。だって先月も同じことをしたんだから。
でも、じゃあ、他に何をすればいい?こんな状況で。やってしまう前に戻れるタイムマシンがいまここにあったのならば。何に変えてでも、どんな作用を未来に及ぼしたとしてもかまわない。恐れず乗り込み、そのミスを見つけ出す未来を選択してきますと約束するのに。
反省していたし、気を付けてもいたのにどうして?
あなたの代わりなんていくらでもいます。あなたみたいなやる気のない人は、うちにはいりません。今すぐ現場に異動してもらってもいいんですよ。
申し訳ございません。
謝って、改善策を出しても何も変わらないじゃない。頑張っていく気がないのなら、何をしても同じでしょう。
顔をくしゃくしゃにして、上司の冷めた怒号を聞きながら、けれども私はミスの原因を理解していた。そう、上司の言うことは正しい。
やる気。
そんなものなかった。
ただ給料をもらえればそれで良かった。日陰の仕事でもなんでも、ただ怒られずに黙々と仕事をこなして、25日に給料が振り込まれればそれでよかった。のぼりつめたいわけじゃない。正社員でいたいわけでもない。ほんとうはアルバイトでもパートでもなんでもよかった。
でも、実家には帰りたくなかった。だから厳格な父や祖父を納得させるだけのそれなりの仕事に就く必要があった。
就活は完敗した。就活なんて気持ち悪いと思っていたらまわりの人はすでに大手企業や公務員に仕事が決まっていた。焦って就活を始めたが時すでに遅しとはこのこと。成績なんて中の下だった私に誇れるものといえば、サークルだけだったが、副部長なんてあってもなくても構わなかった肩書きなんて、いまどきの就活ではほとんどの人が使っているものだった。
自慢できるような業績も残せなかった。後輩をうまく育て上げることすらできなかった。
最後の最後で拾ってくれた会社は、いわゆるブラック企業というものではなかったが、私には、とうてい受け入れられない考えを持つ会社だった。
そしてなにより、私には他にやりたいことがあった。小説を書くことだ。
もちろんそれで有名になろうとは思っていないし、出来ないだろうとすでに諦めていた。高校生まで友達に夢を話していたが、今では仲の良いひとにすら言わなかった。すごいねー!とうわべでは言っても、心の中で笑われる、ばかにされることは明白だった。その年齢でまだそんなこと言ってるの?そっかあ無理なのにいまだに信じてるんだなあ。ちょっと痛いかも・・・・。
そんな空気をひしひしと感じ始めて以来、私は決して口には出さず、心にだけ留めた。
自分でも無理だとわかっていながら。
それでも書きたいという微かなホタルの光のような弱々しい欲望にしがみついて。
結局その日もなんとか難を逃れた。難ってなんだろう。怒りの嵐をやりすごしたことか、部署異動させられなかったことか、クビにならなかったことか。そもそも逃れたのが良かったことだったのかは分からない。
時々思う。
辞表を突きつけて辞めますと言えたら。
会社をずる休みして寝過ごせたら。
ある日突然出勤しなくなって、そのままどこか遠くへ行けたら。
けれども、私にはどれも出来なかった。出勤しなかった次の日のことを考えれば、行くことよりもさらに憂鬱だった。胃の辺りがきりきりと痛む。大学受験に失敗した高校3年の夏を思い出す懐かしい痛みだ。あの頃ちぎれるような痛みに苦しみながら浪人し、晴れて目指した大学に行けた私は、こんなことをするために頑張ったのだろうか。
だとしたら、なんてばかみたいな努力だったんだろう。
こんな未来が待っているのだと知ったら。
今頃ここにいないのか。
いいや。わたしは自嘲気味に笑った。そんな度胸なんてない。もはやどうしようもない人生を生きるしかないのだろう。
家に帰って、パソコンを開く。書きかけの小説の前に座る。文章を眺めた。しかし何の言葉も浮かんでこない。いつからか、書くという事にまで、無関心になっていった。そのことに気付きたくなくて、心は空っぽなのにパソコンは毎日開いた。けれども、そんなわたしが綴る物語は、いつの間にか自分さえ肯定できないほどの何の面白味もない文章になっていった。
なんて覇気のない文章なんだろう。
なんて義務感にあふれた文章なんだろう。
なんてつまらなそうに生きているんだろう。
わたしは、静かにパソコンを閉じた。
もう、希望なんてどこにもない。
このまま頭を下げ続けて、嵐を逃れ、おびえながら、それでもお金のためだけに生きる。
3年頑張れ
5年頑張れ
辞めたいと2年ごとにつぶやいた弟に対して、発した父の言葉がよみがえってきた。
耐えて耐えて耐えて耐えて耐えて耐えて耐えて
その先に何が残る?
その先に何を求める?
その先がないのならば。
なぜ生きるのか。
もはやわたしにはなにもわからない。
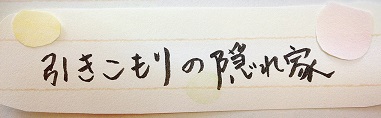
心の奥の灯りをそっと想い出す、小さな隠れ家。

もう同じ生き方ではいられない… そう静かに感じはじめているあなたへ


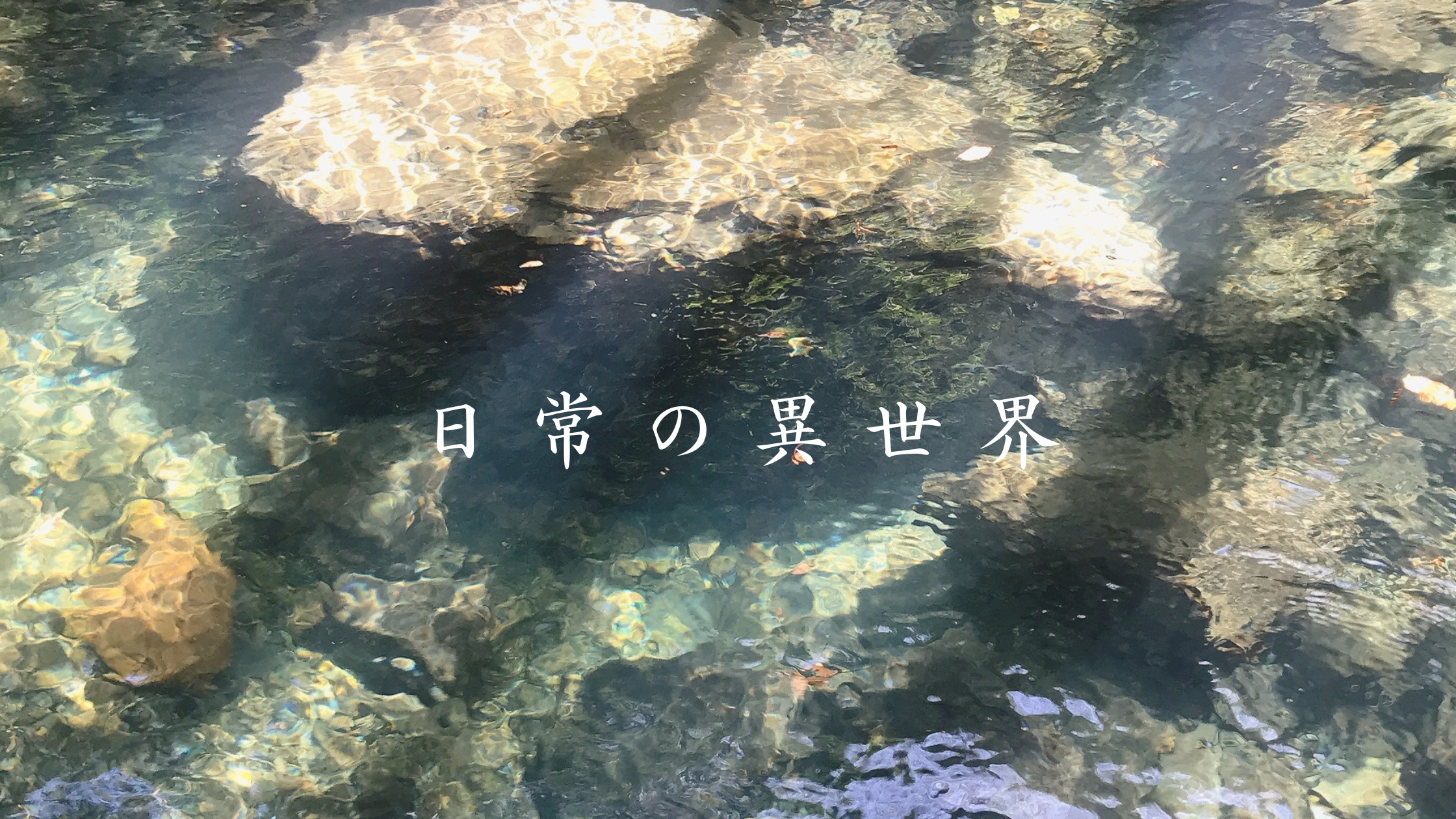

コメント
この記事へのトラックバックはありません。









この記事へのコメントはありません。